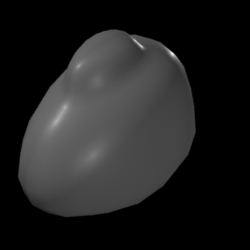mqo2rib(metared)
- Metasequoia
- by yuichirou yokomakura
- 2010.09.10 Friday 21:57
b2oxさん開発のRIBエクスポータ、webarchiveで探してダウンロードしました。
メタセコイアをRIBに変換しようとコマンドプロンプトから、打ったらエラー。
>mqo2rib.exe men_test.mqo
"men_test.mqo" is now loading and converting... Format Error at line 13, column 1 in "men_test.mqo".
complete! (Elapsed time: 0.0s)
検索したら、mqoファイル内にマテリアルが設定されていないからということがわかりました。メタセコイアで開いて、材質パネルで新規mat1を設けて上書き保存。こんどはできました。
3Delightでレンダリングしました。
mqo2rib.cfgをエディタで開き、コメントアウトを外す
RIB[:Renderer] = '3Delight'
付属のシェーダdistantlight2.slは、
shaderdl distantlight2.sl
でコンパイルしておきます。
レンダリングすると、下記のエラー
3DL ERROR P1107: [.../men_test.rib:27]: user p
arameter 'shadowname' has an unknown type
タイプを記述しておきました。
typeはshaderinfoでしらべるとわかります。
LightSource "distantlight2" 1
"uniform string shadowname" ["raytrace"]
"from" [0.236593 1.226111 -0.110574]
"uniform float shadowpower" [0.5]
"to" [0.000000 0.000000 0.000000]
"lightcolor" [1.000 1.000 1.000]
"uniform float blur" [0.03]
"uniform float samples" [10]
後、法線の計算で8点計算されて出力されました。
3DL WARNING P1104: [men_test_mdl.rib:13]:
array of 'normal's has wrong size, expected 18 'normal'(s), but given 24
"N" [0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.980581 -0.196116
0.000000 0.980581 -0.196116
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.980581 0.196116
0.000000 0.980581 0.196116
0.000000 1.000000 -0.000000]
5行目
0.000000 1.000000 -0.000000
と8行目
0.000000 1.000000 -0.000000
を削除した。
レンダリングでエラーが出なくなった。
mqo2rib使ってみます。
ありがとうございます。
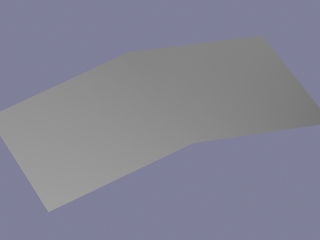
メタセコイアをRIBに変換しようとコマンドプロンプトから、打ったらエラー。
>mqo2rib.exe men_test.mqo
"men_test.mqo" is now loading and converting... Format Error at line 13, column 1 in "men_test.mqo".
complete! (Elapsed time: 0.0s)
検索したら、mqoファイル内にマテリアルが設定されていないからということがわかりました。メタセコイアで開いて、材質パネルで新規mat1を設けて上書き保存。こんどはできました。
3Delightでレンダリングしました。
mqo2rib.cfgをエディタで開き、コメントアウトを外す
RIB[:Renderer] = '3Delight'
付属のシェーダdistantlight2.slは、
shaderdl distantlight2.sl
でコンパイルしておきます。
レンダリングすると、下記のエラー
3DL ERROR P1107: [.../men_test.rib:27]: user p
arameter 'shadowname' has an unknown type
タイプを記述しておきました。
typeはshaderinfoでしらべるとわかります。
LightSource "distantlight2" 1
"uniform string shadowname" ["raytrace"]
"from" [0.236593 1.226111 -0.110574]
"uniform float shadowpower" [0.5]
"to" [0.000000 0.000000 0.000000]
"lightcolor" [1.000 1.000 1.000]
"uniform float blur" [0.03]
"uniform float samples" [10]
後、法線の計算で8点計算されて出力されました。
3DL WARNING P1104: [men_test_mdl.rib:13]:
array of 'normal's has wrong size, expected 18 'normal'(s), but given 24
"N" [0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.980581 -0.196116
0.000000 0.980581 -0.196116
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.980581 0.196116
0.000000 0.980581 0.196116
0.000000 1.000000 -0.000000]
5行目
0.000000 1.000000 -0.000000
と8行目
0.000000 1.000000 -0.000000
を削除した。
レンダリングでエラーが出なくなった。
mqo2rib使ってみます。
ありがとうございます。
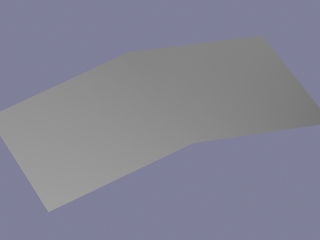
- -
- -