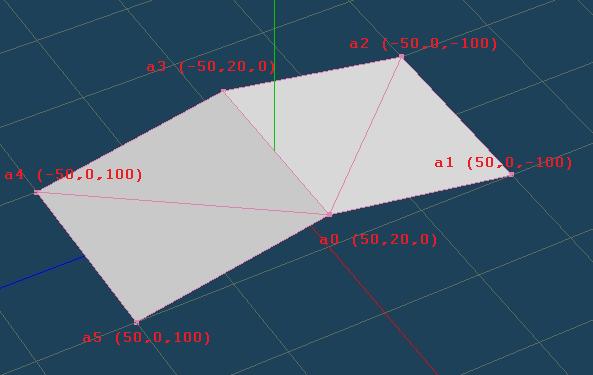メタセコイアでPython練習 テキスト処理
- Metasequoia > Metasequoia Python
- by yuichirou yokomakura
- 2010.09.06 Monday 00:12
metasequoia pythonスクリプトで、基本となるファイルの書き出しをやってみました。テキストファイルですが、はじめの一歩となります。
リストa=['mother','other','test']をadd.txtというファイルに改行して保存します。スクリプト実行時にリストの個数を数えて、表示するようにしています。ファイル出力の基礎基本、大切ですね。さらに勉強します。
リストa=['mother','other','test']をadd.txtというファイルに改行して保存します。スクリプト実行時にリストの個数を数えて、表示するようにしています。ファイル出力の基礎基本、大切ですね。さらに勉強します。
def p(*args):
"""
プリント関数
複数の引数を渡せる。
"""
if len(args)==0:
# 改行させる
MQSystem.println("")
return
for arg in args:
MQSystem.println(str(arg))
#meta_text.py リストを作成し、保存する。
doc = MQSystem.getDocument()
out = MQSystem.println
import traceback
import sys
try:
a=['mother','other','test']
b=len(a)
for i in range(b):
out(str(a[i]))
o=open('add.txt','w')
for x in a:
o.write(x+'\n') #改行を加える
o.close()
except:
info=sys.exc_info()
p(info[0])
p(info[1])
p(*traceback.extract_tb(info[2]))- -
- -